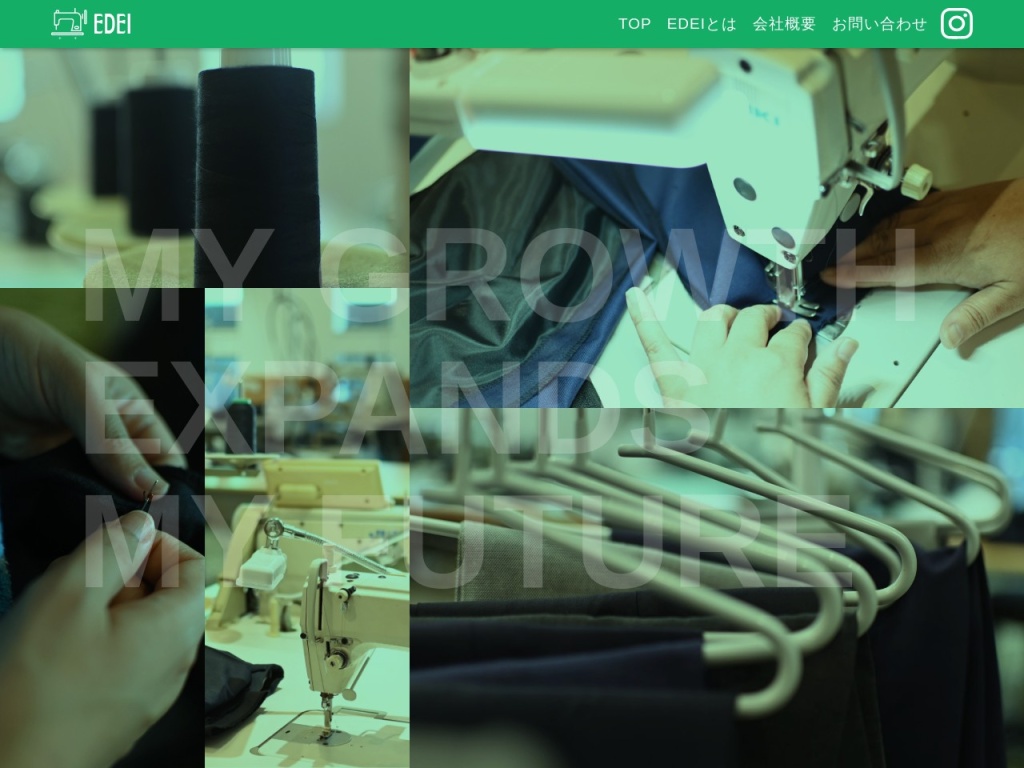ITシステムで発生する予期せぬトラブル、すなわち「インシデント」への対応に課題を感じていませんか?インシデント管理の目的は、単なる場当たり的な障害対応ではなく、ビジネスへの影響を最小限に抑え、ITサービスの品質と顧客満足度を維持・向上させることにあります。本記事では、インシデント管理の基本的な定義や問題管理との違いから、検知・記録・解決に至る具体的なプロセス、サービスデスクなどの体制構築、さらにはITSMツールの選び方までを網羅的に解説します。最後まで読めば、自社のインシデント管理を成功に導くための具体的な方法論を理解し、サービス品質の向上につなげることができます。
インシデント管理とは何か
インシデント管理とは、ITサービスにおいて発生した計画外のサービス中断や品質低下(インシデント)から、可能な限り迅速にサービスを正常な状態に復旧させ、事業への影響を最小限に抑えるためのプロセスのことです。世界的なITサービスマネジメントの成功事例をまとめたフレームワークである「ITIL(Information Technology Infrastructure Library)」でも、中心的なプロセスの一つとして定義されています。
システムトラブルやユーザーからの問い合わせに対し、場当たり的に対応するのではなく、体系化されたプロセスに沿って記録、対応、解決、報告を行うことで、ITサービスの安定稼働と品質維持を目指します。これにより、ビジネスの継続性を確保し、顧客満足度や企業への信頼を維持・向上させる重要な役割を担っています。
インシデントの定義と具体例
ITILにおける「インシデント」とは、「ITサービスの品質を低下させる、あるいは低下させる可能性のある、計画外の出来事」と定義されています。これは、サービスが完全に停止するような重大な障害だけでなく、パフォーマンスの低下や一部機能の不具合など、ユーザーの業務に支障をきたすあらゆる事象を含みます。
インシデントの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 社内システムにログインできない
- 業務用アプリケーションの動作が極端に遅い
- メールの送受信ができない
- Webサイトの特定のページが表示されない
- プリンターから印刷ができない
- サーバーがダウンしてサービスが完全に停止した
これらの事象が発生した際に、迅速に検知し、影響範囲を特定し、サービスを復旧させることがインシデント管理の最初のステップとなります。
インシデント管理と混同されやすい用語との違い
インシデント管理を正しく理解するためには、関連するいくつかの用語との違いを明確に区別することが重要です。特に「問題管理」「障害管理」「変更管理」は密接に関連していますが、それぞれ目的と役割が異なります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。
問題管理との違い
インシデント管理と最も混同されやすいのが「問題管理」です。インシデント管理の目的が「サービスの迅速な復旧(応急処置)」であるのに対し、問題管理は「インシデントの根本原因を特定し、恒久的な解決策を見つけて再発を防止すること」を目的とします。
例えば、「サーバーがダウンした」というインシデントに対し、サーバーを再起動してサービスを復旧させるのがインシデント管理です。一方、なぜサーバーがダウンしたのか(例:メモリ不足、特定のプログラムのバグなど)という根本原因を調査し、メモリ増設やプログラム修正といった恒久対策を行うのが問題管理の役割です。
障害管理との違い
「障害」は、インシデントの中でも特にITサービスの構成要素(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど)が故障・停止し、サービスが提供できなくなった状態を指す言葉として使われることが一般的です。つまり、障害はインシデントの一種と捉えることができます。
インシデントは「サービス品質の低下」全般を指す広い概念であり、「Webページの表示が少し遅い」といった軽微な事象も含まれます。組織によっては「インシデント」と「障害」をほぼ同義で使う場合もありますが、ITILのフレームワーク上では、インシデントという大きな枠組みの中に障害が含まれると理解しておくと良いでしょう。
変更管理との違い
「変更管理」は、ITインフラやサービスに対するすべての変更(例:サーバーの交換、ソフトウェアのアップデート、設定の変更など)を管理するプロセスです。その目的は、変更に伴うリスクを評価し、サービスへの悪影響を最小限に抑えながら、計画的かつ安全に変更を実施することです。
インシデント管理が「計画外の出来事」に対する事後対応であるのに対し、変更管理は「計画的な作業」に対する事前対応という点で大きく異なります。ただし、不用意な変更がインシデントを引き起こす原因となることも多いため、インシデント管理と変更管理は密接に連携する必要があります。
| 管理プロセス | 目的 | 対応フェーズ | 主なアクション |
|---|---|---|---|
| インシデント管理 | サービスの迅速な復旧と影響の最小化 | 事後対応(応急処置) | 暫定的な回避策の適用、再起動、ユーザーへの状況報告 |
| 問題管理 | 根本原因の特定と再発防止 | 事後対応(恒久対策) | 原因調査、分析、恒久的な解決策の策定と実装 |
| 変更管理 | 変更に伴うリスクの最小化と安全な実施 | 事前対応(計画) | 変更計画の立案、影響評価、承認、リリース管理 |
インシデント管理の目的とビジネスにおける重要性
インシデント管理は、単に発生したITトラブルを場当たり的に解決するための活動ではありません。その本質は、ビジネスへの悪影響を最小限に食い止め、サービスの安定性を確保し、最終的には顧客からの信頼を維持・向上させることにあります。ここでは、インシデント管理がビジネスにおいてなぜ重要なのか、その3つの主要な目的を深掘りします。
事業への影響を最小限に抑える
ITシステムやサービスで発生するインシデントは、ビジネスに直接的な損害をもたらします。例えば、ECサイトが停止すれば売上はゼロになり、基幹システムがダウンすれば全社の業務が停滞します。インシデント管理の最も重要な目的は、インシデントの発生から解決までの時間(ダウンタイム)を可能な限り短縮し、事業へのダメージを最小限に抑えることです。
インシデントがビジネスに与える影響は、多岐にわたります。
| 影響の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 直接的な金銭的損失 | ECサイトの停止による売上機会の損失、決済システムの障害による取引停止、SLA違反による違約金の発生など。 |
| 生産性の低下 | 社内システムの停止による従業員の業務停滞、コミュニケーションツールの不具合による連携ミス、データアクセスの遅延など。 |
| 機会損失 | Webサイトの表示不良による新規顧客獲得の機会逸失、オンライン商談システムの不具合による取引の中断など。 |
| 追加コストの発生 | 緊急対応のための人件費、外部専門家への依頼費用、データ復旧にかかる費用、顧客へのお詫びにかかる費用など。 |
確立されたインシデント管理プロセスがあれば、インシデントを迅速に検知し、適切な担当者へエスカレーションし、定義された手順に沿って復旧作業を進めることができます。これにより、サービス停止時間を短縮し、上記のようなビジネスインパクトを最小限に食い止めることが可能になります。
ITサービスの品質と可用性を維持する
現代のビジネスにおいて、ITサービスは事業継続の基盤そのものです。顧客に安定した価値を提供し続けるためには、ITサービスの「品質」と「可用性」を高いレベルで維持することが不可欠です。
- 品質(Quality): サービスが、利用者の期待する機能や性能を安定して提供できている状態。
- 可用性(Availability): 利用者が必要な時に、いつでもサービスを利用できる状態。
インシデント管理は、サービスレベルアグリーメント(SLA)で定められた可用性の目標値を達成するための中心的な役割を担います。インシデントが発生するとサービスの品質や可用性は低下するため、迅速な復旧対応が求められます。また、発生したインシデントの内容、原因、対応策をすべて記録・分析することで、システムの弱点を特定し、再発防止策を講じることが可能になります。これにより、ITサービス全体の安定性が向上し、継続的な品質改善へと繋がっていくのです。
顧客満足度と信頼を向上させる
顧客にとって、利用しているサービスが頻繁に停止したり、不具合が放置されたりすることは、大きなストレスとなります。サービスの不安定さは顧客満足度の低下に直結し、最悪の場合、競合他社への乗り換え、すなわち顧客離れ(チャーン)を引き起こします。
優れたインシデント管理体制は、障害発生というネガティブな事象を、逆に顧客からの信頼を獲得する機会に変えることができます。たとえインシデントが発生してしまっても、迅速な検知、透明性のある情報提供、そして誠実な復旧対応を行うことで、顧客は「この企業は信頼できる」と感じるようになります。
例えば、サービス障害発生時に「現在、原因を調査中です。進捗は30分ごとにご報告します」といった具体的なコミュニケーションを行うことで、顧客の不安を和らげることができます。このように、インシデントへの対応品質は、顧客ロイヤルティや企業のブランドイメージを左右する重要な要素であり、長期的なビジネスの成功に不可欠です。
インシデント管理の基本的なプロセスとフロー
インシデント管理は、場当たり的に対応するのではなく、体系化されたプロセスに沿って進めることが不可欠です。ここでは、ITサービスマネジメントのベストプラクティス集である「ITIL(Information Technology Infrastructure Library)」で定義されている、世界標準の基本的なプロセスとフローを6つのステップに分けて解説します。
ステップ1 検知と記録
インシデント管理の最初のステップは、インシデントの発生を「検知」し、その内容を正確に「記録」することです。検知のきっかけは、ユーザーからの電話やメール、チャットでの問い合わせ、あるいは監視ツールが発するシステム異常のアラートなど多岐にわたります。
インシデントを検知したら、速やかに管理システムに「チケット」として起票します。記録すべき主な情報は以下の通りです。
- インシデントの発生日時
- 報告者の氏名・部署・連絡先
- インシデントの概要(どのような事象が起きているか)
- 発生しているシステムやサービスの名称
- エラーメッセージの内容
この段階で情報を正確かつ網羅的に記録することが、後のステップをスムーズに進めるための鍵となります。すべてのインシデントを一元的に管理し、対応漏れや重複を防ぐための重要な工程です。
ステップ2 分類と優先度付け
記録されたインシデントは、次に「分類」と「優先度付け」が行われます。これにより、適切な担当者へ迅速に割り当て、対応の順序を決定します。
「分類」では、インシデントの内容に応じて「ネットワーク障害」「サーバー障害」「アプリケーションの不具合」「アカウント関連の問い合わせ」といったカテゴリに分けます。これにより、どの専門チームが対応すべきかが明確になります。
「優先度付け」は、インシデントがビジネスに与える影響の大きさを客観的に判断するために極めて重要です。一般的には、以下の表のように「影響度(インパクト)」と「緊急度(アージェンシー)」の2つの軸を組み合わせたマトリクスで決定します。
| 緊急度:高 (すぐに解決が必要) | 緊急度:中 (業務時間内に解決が必要) | 緊急度:低 (数日中の解決で可) | |
|---|---|---|---|
| 影響度:大 (基幹システム停止など) | 最優先 | 高 | 中 |
| 影響度:中 (一部門の業務停止など) | 高 | 中 | 低 |
| 影響度:小 (個人PCの不具合など) | 中 | 低 | 低 |
この優先度に基づき、限られたリソースを最も重要なインシデントから順に割り振ることで、ビジネスへのダメージを最小限に食い止めます。
ステップ3 調査と診断(一次対応)
優先度付けが終わると、インシデントは一次対応担当者である「サービスデスク」に割り当てられ、具体的な調査と診断が開始されます。サービスデスクは、まずインシデントの詳細をユーザーからヒアリングし、状況の正確な把握に努めます。
次に、過去の対応履歴が蓄積された「ナレッジベース」やFAQを検索し、同様の事象が過去になかったかを確認します。既知の問題であれば、ナレッジに記載された手順に従って迅速に解決を図ります。パスワードのリセットや基本的な操作方法の案内など、簡易なインシデントの多くはこの段階で解決されます。
ステップ4 エスカレーション(二次・三次対応)
一次対応で解決が困難な場合や、より専門的な知識・権限が必要だと判断された場合は、インシデントを上位の専門チームへ「エスカレーション」します。
- 二次対応: サーバー、ネットワーク、データベースなど、特定の技術領域に特化した専門チームが対応します。より詳細なログ解析やシステムの調査を行います。
- 三次対応: 製品の開発元や外部のベンダーなど、社内だけでは解決できない高度な問題に対応します。
エスカレーションを行う際は、これまでの調査内容やユーザーとのやり取りを正確に引き継ぐことが重要です。情報伝達が不十分だと、同じ質問をユーザーに繰り返すことになり、顧客満足度の低下につながるため注意が必要です。
ステップ5 解決と復旧
エスカレーションを受けた担当者、あるいは一次対応担当者が、インシデントの原因を特定し、解決策を実施します。解決策には、システムの設定変更、パッチの適用、ハードウェアの交換といった恒久的な対策のほか、代替手段の提供といった暫定的な回避策も含まれます。
インシデント管理における最大の目的は「迅速なサービス復旧」です。そのため、根本的な原因究明に時間をかけるよりも、まずはサービスを正常な状態に戻すことを最優先します。根本原因の分析と恒久対策の検討は、サービス復旧後、別途「問題管理」のプロセスで行われます。
解決策を実施した後は、サービスが正常に稼働していることを確認し、インシデントを報告したユーザーに復旧を連絡します。
ステップ6 クローズとナレッジ化
ユーザーからサービスが正常に復旧したことの同意を得られたら、インシデントのチケットを「クローズ(完了)」します。これで一連の対応は終了となります。
しかし、ここで終わらせてはいけません。今回のインシデント対応で得られた知見を、組織全体の資産として活用するために「ナレッジ化」する工程が非常に重要です。対応の経緯、原因、具体的な解決手順などをナレッジベースに登録することで、将来発生するであろう同様のインシデントに対して、誰もが迅速かつ的確に対応できるようになります。このナレッジの蓄積こそが、組織全体のインシデント対応能力を向上させる原動力となるのです。
インシデント管理を支える体制と各役割
インシデント管理を効果的に機能させるためには、インシデントの発生から解決までをスムーズに進めるための体制構築と、各担当者の役割分担の明確化が不可欠です。国際的なITサービスマネジメントのフレームワークであるITIL(Information Technology Infrastructure Library)でも、これらの役割定義が重要視されています。ここでは、代表的な体制とそれぞれの役割について詳しく解説します。
サービスデスク(一次窓口)
サービスデスクは、ユーザーからの問い合わせやインシデント報告を受け付ける最初の窓口(SPOC: Single Point of Contact)です。インシデント管理の起点となる非常に重要な役割を担います。
主な役割は、インシデントの受付、内容の正確な記録、優先順位の初期判断、そして過去の事例やナレッジベースを基にした一次対応です。簡単なインシデントであれば、この段階で解決することもあります。サービスデスクの対応品質が、ユーザーの満足度とインシデント解決までの時間に直結するため、迅速かつ丁寧なコミュニケーション能力と、幅広い基礎知識が求められます。
一次対応で解決できない場合は、インシデントの内容を正確に分析し、後述する技術スペシャリストチームへ引き継ぐ(エスカレーションする)役割も担います。
インシデントマネージャー
インシデントマネージャーは、インシデント管理プロセス全体が円滑に機能するように監督・指揮する責任者です。個別の技術的な問題解決に直接関わるのではなく、プロセス全体のオーナーとして、司令塔の役割を果たします。
特に、事業への影響が大きい重大なインシデントが発生した際には、関係部署間の連携を促進し、コミュニケーションを統制しながら、SLA(サービスレベル合意書)に基づいて迅速なサービス復旧を主導します。また、インシデント対応の進捗を経営層や関係者に報告し、対応後のレビューを通じてプロセスの改善点を洗い出し、再発防止策の検討を促すことも重要な責務です。
技術スペシャリストチーム
技術スペシャリストチームは、サービスデスクでは解決できない、より専門的な知識や技術を必要とするインシデントの調査と解決を担当する専門家集団です。二次対応や三次対応を担うチームであり、ネットワーク、サーバー、データベース、アプリケーションといった専門領域ごとに構成されるのが一般的です。
サービスデスクからエスカレーションされた情報をもとに、ログの解析、システムの詳細調査、再現テストなどを行い、インシデントの根本原因を特定します。恒久的な解決策が見つかるまでの間、ビジネスへの影響を最小限に抑えるための暫定的な回避策(ワークアラウンド)を提供することも、このチームの重要な役割です。解決したインシデントの情報は、ナレッジベースに蓄積し、将来同様のインシデントが発生した際に迅速に対応できるよう貢献します。
各役割の責任範囲まとめ
インシデント管理における各役割の責任範囲をまとめると、以下のようになります。
| 役割 | 主な責任範囲 | インシデント対応におけるフェーズ |
|---|---|---|
| サービスデスク | ユーザーからの問い合わせ受付、インシデントの記録、一次切り分け、簡単な問題の解決、エスカレーション | 一次対応 |
| インシデントマネージャー | プロセス全体の監督・指揮、重大インシデント発生時の統制、SLAの遵守管理、関係者への報告、プロセスの改善 | プロセス全体 |
| 技術スペシャリストチーム | 専門的な調査・診断、原因特定、回避策の提供、恒久的な解決策の実装、ナレッジの蓄積 | 二次・三次対応 |
このように、各チームや担当者が自身の役割と責任を明確に理解し、互いに連携することで、組織全体としてインシデントに強く、迅速に対応できる体制が構築されます。
インシデント管理に役立つおすすめツール
インシデント管理を迅速かつ効率的に行うためには、ツールの活用が不可欠です。Excelやスプレッドシートによる手動管理では、対応漏れや情報共有の遅れ、属人化といった問題が発生しやすくなります。適切なツールを導入することで、インシデント管理プロセス全体を可視化し、標準化されたワークフローに沿って対応を進めることが可能になります。
ここでは、インシデント管理の目的や規模に応じて活用できるツールを「ITSMツール」「プロジェクト管理ツール」「コミュニケーションツール」の3つのカテゴリに分けてご紹介します。
ITSMツール(ServiceNow, Jira Service Management)
ITSM(ITサービスマネジメント)ツールは、インシデント管理を含むITILに基づいたITサービス運用全般を支援するために設計された専門ツールです。インシデントの受付から記録、優先度付け、担当者の割り当て、SLA(サービスレベル合意書)の管理、解決、クローズまでの一連のプロセスを一元管理できます。
インシデント管理のプロセスを本格的に標準化し、継続的な改善を目指す企業にとって最も効果的な選択肢です。レポート機能やダッシュボード機能も充実しており、対応状況の可視化やKPIの分析に大きく貢献します。
| ツール名 | 主な特徴 | 特に推奨される企業 |
|---|---|---|
| ServiceNow | ITILに準拠した包括的な機能を提供し、インシデント管理だけでなく問題管理や変更管理など、ITSMプロセス全体を統合管理できるプラットフォームです。カスタマイズ性が非常に高く、大規模で複雑な組織の要件にも対応可能です。 | ITILに準拠した本格的なITSMを全社的に導入したい大企業 |
| Jira Service Management | 開発管理ツール「Jira」との連携に強みを持ち、インシデントの原因がソフトウェアのバグである場合に、開発チームへのエスカレーションや情報連携をスムーズに行えます。直感的なインターフェースで、比較的導入しやすいのが特徴です。 | 開発部門との連携を重視する企業、アジャイル開発を取り入れている企業 |
プロジェクト管理ツール(Backlog, Redmine)
プロジェクト管理ツールは、本来タスクや課題を管理するためのツールですが、その機能を応用してインシデント管理に活用することも可能です。インシデントを一つの「タスク」や「チケット」として登録し、担当者、期限、進捗状況を管理します。
ITSMツールほど専門的な機能はありませんが、多くの企業で既に導入されているケースが多く、手軽に始められる点がメリットです。特に、インシデント対応が複数のタスクに分解される場合や、開発チームと連携して解決にあたる場合に有効です。
| ツール名 | 主な特徴 | 特に推奨される企業 |
|---|---|---|
| Backlog | 日本の企業が開発しており、直感的で分かりやすいUIが特徴です。エンジニアだけでなく、マーケターや営業担当者など、ITに詳しくないメンバーでも使いやすく、全社的な情報共有ツールとしても活用できます。 | IT部門以外も含む幅広いメンバーでインシデント情報を共有したい企業 |
| Redmine | オープンソースであるため、自社サーバーに無料で構築できます。プラグインが豊富にあり、自社の運用に合わせて柔軟に機能を拡張できる高いカスタマイズ性が魅力です。 | コストを抑えつつ、自社の運用に合わせてシステムを柔軟に構築したい企業 |
コミュニケーションツール(Slack, Microsoft Teams)
インシデント発生時には、関係者間での迅速かつ正確な情報共有が極めて重要です。ビジネスチャットなどのコミュニケーションツールは、このリアルタイムな連携を強力にサポートします。
インシデント対応専用のチャンネル(チャネル)を作成し、関係者を集約することで、状況の共有、対応方針の協議、意思決定をスピーディに行うことができます。また、やり取りの履歴が時系列で保存されるため、後から対応経緯を振り返る際や報告書を作成する際にも役立ちます。ITSMツールやプロジェクト管理ツールと連携させることで、インシデントの発生通知を自動で投稿するなど、さらなる効率化が図れます。
| ツール名 | 主な特徴 | 特に推奨される企業 |
|---|---|---|
| Slack | 外部サービスとの連携機能(インテグレーション)が非常に豊富で、様々なツールからの通知をSlackに集約できます。カスタマイズ性が高く、ワークフローの自動化なども容易に設定可能です。 | 多数の外部ツールと連携させ、情報共有のハブとして活用したい企業 |
| Microsoft Teams | Microsoft 365(Office 365)との親和性が非常に高く、WordやExcel、SharePointなどとの連携がスムーズです。Web会議機能も統合されており、チャットからシームレスにオンラインミーティングを開始できます。 | 既にMicrosoft 365を全社的に導入・活用している企業 |
インシデント管理を成功に導く5つのコツ
インシデント管理のプロセスや体制を構築しても、それらが効果的に機能しなければ意味がありません。ここでは、インシデント管理を形骸化させず、ビジネスの安定運用に真に貢献させるための5つの重要なコツを解説します。これらのポイントを実践することで、インシデント対応の質と速度を飛躍的に向上させることが可能です。
対応プロセスと役割分担を明確にする
インシデント発生時、最も避けなければならないのは「誰が何をすべきか分からない」という混乱状態です。対応の遅れは、ビジネスへの影響を直接的に拡大させます。これを防ぐためには、あらかじめ対応プロセスと各担当者の役割・責任を文書化し、関係者全員がいつでも参照できる状態にしておくことが不可欠です。
具体的には、インシデントの検知からクローズまでの各ステップにおいて、「誰が」「何を」「いつまでに行うか」を定義したワークフローを作成します。特に、一次対応で解決できない場合に誰にエスカレーションするのか、その基準を明確に定めておくことが重要です。これにより、インシデント発生時に担当者が迷う時間をなくし、迅速かつ的確な初期対応とエスカレーションを実現することが、被害を最小限に食い止める鍵となります。
役割分担を定義する際には、RACIチャート(実行責任者、説明責任者、協業先、報告先を明確にするフレームワーク)などを活用すると、責任の所在がより明確になります。
SLA(サービスレベル合意書)を設定し遵守する
SLA(Service Level Agreement)とは、サービス提供者と利用者の間で合意するサービス品質の基準です。インシデント管理においては、「いつまでに対応を開始し(目標応答時間)」「いつまでに解決するか(目標復旧時間)」といった目標値を具体的に定めます。SLAを設定することで、対応の優先順位付けが客観的な基準で行えるようになり、担当者の判断にブレがなくなります。
SLAは、インシデントのビジネスへの影響度や緊急度に応じて、複数のレベルを設定するのが一般的です。例えば、以下のように定義します。
| 優先度 | 定義(例) | 目標応答時間 | 目標復旧時間 |
|---|---|---|---|
| 最高(緊急) | 全社的なシステム停止など、事業継続に深刻な影響 | 15分以内 | 1時間以内 |
| 高 | 主要機能の停止など、多くのユーザーに影響 | 1時間以内 | 4時間以内 |
| 中 | 一部機能の不具合など、影響範囲が限定的 | 4時間以内 | 8営業時間以内 |
| 低 | 軽微な不具合や問い合わせ | 8営業時間以内 | 3営業日以内 |
SLAは単なる努力目標ではなく、顧客やサービス利用者との「約束」です。この基準を組織全体で共有し、遵守する文化を醸成することが、ITサービスの信頼性向上に直結します。
ナレッジベースを整備し積極的に活用する
インシデント対応は、一度きりの使い捨ての作業ではありません。対応の過程で得られた知見や解決策は、組織にとって非常に価値のある資産です。過去のインシデント対応履歴や手順書、FAQなどを一元的に蓄積した「ナレッジベース」を整備し、積極的に活用しましょう。
ナレッジベースがあることで、以下のようなメリットが生まれます。
- 対応の迅速化: 過去に類似のインシデントが発生した場合、その時の解決策を参照することで、原因調査や復旧作業の時間を大幅に短縮できます。
- 対応品質の標準化: 担当者のスキルや経験に依存することなく、誰でも一定レベルの対応が可能になり、属人化を防ぎます。
- 新人教育の効率化: 新しいメンバーが過去の事例を学ぶことで、早期に戦力となることができます。
インシデントをクローズする際には、対応内容をナレッジベースに登録するプロセスをルール化することが重要です。一つひとつのインシデント対応で得た知見を組織全体の資産として蓄積・活用するサイクルを回すことが、インシデント管理の継続的な改善と効率化を実現します。
KPIを設定し定期的に効果測定と改善を行う
インシデント管理のプロセスがうまく機能しているかを客観的に評価し、改善を続けるためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。「勘」や「感覚」に頼るのではなく、データに基づいた判断を行うことで、プロセスのボトルネックを特定し、的確な改善策を講じることができます。
インシデント管理でよく用いられるKPIには、以下のようなものがあります。
| KPI指標 | 内容 | この指標から分かること |
|---|---|---|
| 平均解決時間(MTTR) | インシデント発生から解決までの平均時間 | 対応プロセ全体の効率性 |
| 初回解決率(FCR) | エスカレーションなしに一次対応で解決できたインシデントの割合 | サービスデスクのスキルレベルとナレッジの充実度 |
| SLA達成率 | 設定したSLAの目標時間内に解決できたインシデントの割合 | サービス品質の遵守レベル |
| 未解決インシデント数 | 特定の期間内にクローズされていないインシデントの数 | 対応チームのキャパシティや対応の遅延状況 |
これらのKPIを定期的に(例えば月次で)集計・分析し、チームでレビューする場を設けましょう。設定したKPIを継続的にモニタリングし、データに基づいてPDCAサイクルを回すことが、インシデント管理の成熟度を着実に高めていくための王道です。
自社に合ったツールを選定し導入する
インシデント管理をメールやスプレッドシートといった手作業で行うには限界があります。インシデントの件数が増えるにつれて、対応漏れや情報共有の遅れ、状況把握の困難さといった問題が顕在化します。これらの課題を解決し、プロセスを効率化するためには、専用ツールの導入が非常に有効です。
インシデント管理ツール(ITSMツールやチケット管理システムとも呼ばれる)を導入することで、以下のようなことが可能になります。
- インシデント情報の一元管理と可視化
- 対応状況のリアルタイムな追跡
- SLAに基づいた優先順位の自動設定と期限管理
- ナレッジベースとの連携
- KPIレポートの自動作成
ツールを選定する際は、価格や機能だけでなく、自社の組織規模やプロセスの成熟度、既存システム(チャットツールや監視ツールなど)との連携性を考慮することが重要です。ただし、ツール導入が目的化しないよう注意が必要です。ツールはあくまで手段であり、まず自社のインシデント管理プロセスを定義し、その運用を円滑にするために最適なツールを選ぶという順序を間違えないことが、導入を成功させるための鉄則です。
まとめ
本記事では、インシデント管理の定義や目的、具体的なプロセス、そして成功に導くための5つのコツについて網羅的に解説しました。
インシデント管理とは、ITサービスの予期せぬ中断や品質低下から迅速に復旧させ、事業への影響を最小限に抑えるための極めて重要な活動です。その本質は、単なる事後対応に留まりません。効果的なインシデント管理プロセスを構築・運用することは、ITサービスの品質と可用性を維持し、顧客満足度と企業全体の信頼性を向上させることに直結します。
ご紹介した検知からクローズまでのフローを確立し、役割分担を明確にするとともに、ナレッジの蓄積と活用、KPIによる継続的な改善を行うことが成功の鍵となります。本記事を参考に、自社のインシデント管理体制を見直し、ビジネスの安定稼働と成長を実現するための一歩を踏み出しましょう。
【PR】関連サイト
SHERPA SUITE
〒108-0073東京都港区三田1-2-22 東洋ビル
URL:https://www.sherpasuite.net/